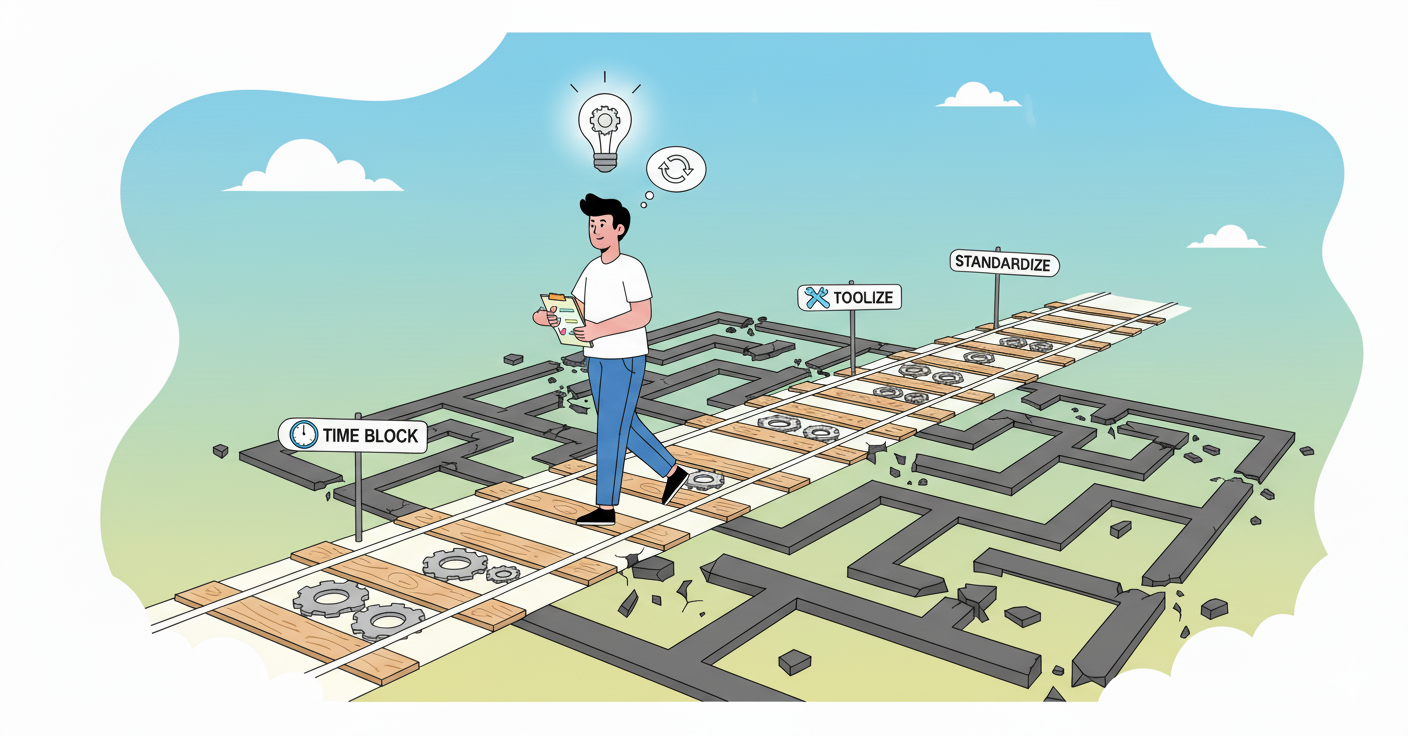この記事で解決できる疑問・悩み
- 自分で何かチャレンジしても途中で挫折しちゃう…
- なんとなく日々のタスクをこなせないことがある…
- 意志が弱いダメな人間なのかな…?
新しいことを始めても長続きしなかったり、日々のやるべきことが思うように進まなかったりして、「自分はダメなのかも…」と落ち込んでしまうことはありませんか。その悩み、実はあなたの意志の力だけが原因ではないかもしれません。大切なのは「頑張る気持ち」だけに頼るのではなく、物事が自然とスムーズに進むような「仕組み」を作ることなのです。
この記事では、そんなあなたの悩みを解決する鍵となる「仕組み化」という考え方をご紹介します。仕組み化のメリットから具体的な実践方法、そして成功のコツまで分かりやすく解説。この記事を読めば、能力や意志力、記憶力に頼らなくても安定して成果を出せるようになり、本当に大切なことに時間を使える、より充実した毎日を送るためのヒントが見つかるはずです。
仕組み化とは?挫折しない自分を作る基本の考え方
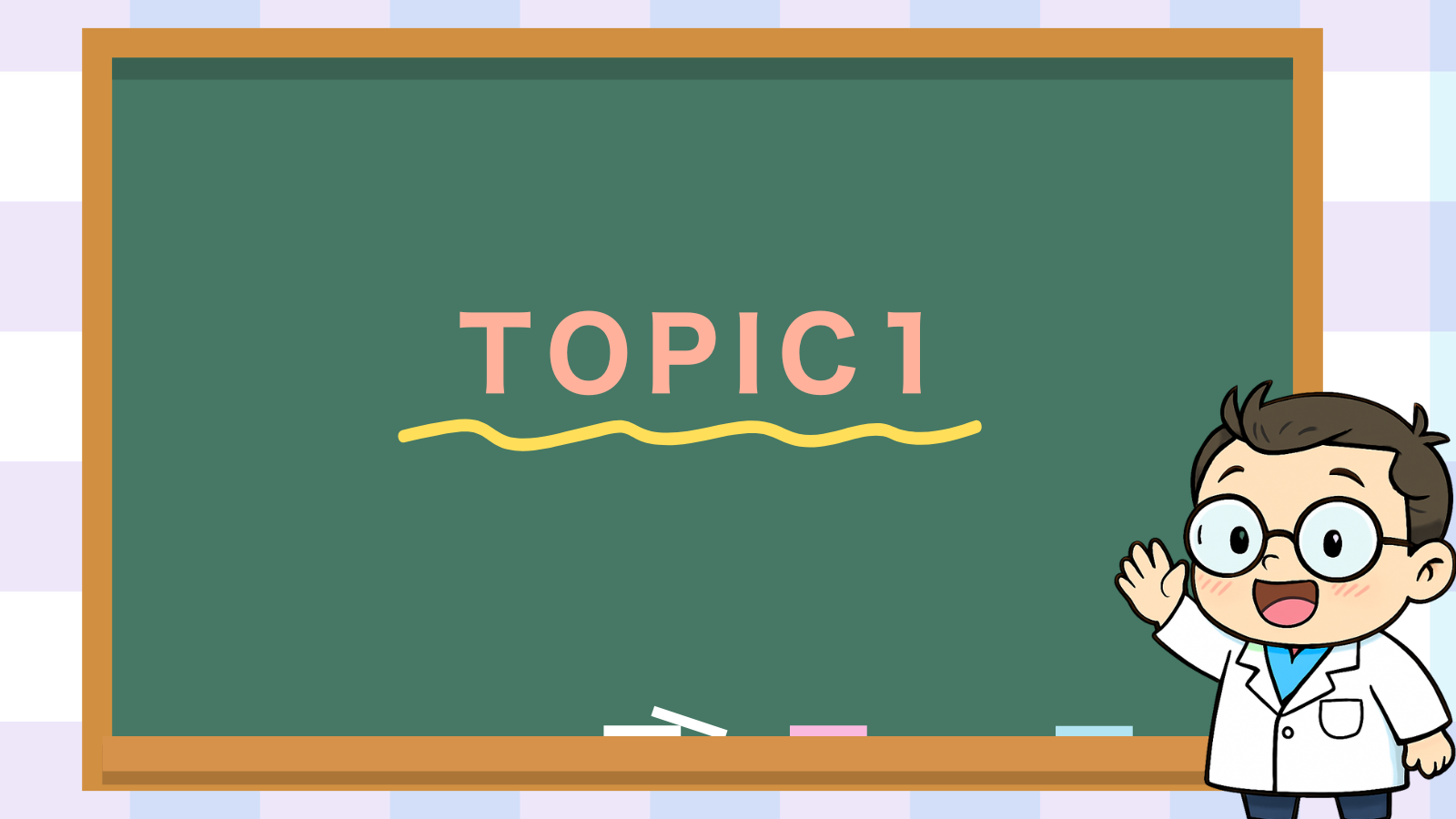


新しい挑戦が続かなかったり、日々のタスクにムラがあったりするのは、あなたの能力や意志だけのせいではありません。多くの場合、物事をスムーズに進めるための「仕組み」が整っていないことが原因です。「仕組み化」とは、個人の能力やその時々の気分、記憶力といった不確かな要素に頼らずとも、安定して物事を進め、望む結果を得るための方法を構築する考え方です。
日常生活にこの「仕組み化」を取り入れることで、面倒な作業も楽にこなせるようになったり、うっかりミスを防いだり、家族との不要なトラブルを減らしたりできます。そして何より、限られた時間を有効に使い、本当に大切なことに集中できるようになるため、QOL(生活の質)向上に不可欠な考え方と言えるでしょう。
「仕組み化」って何?今さら聞けない定義をやさしく解説


仕組み化の基本的な意味
「仕組み化」とは、特定の人の経験や勘、能力に依存せず、業務や作業を進めるための方法や手順を明確に定義し、構築することです。ビジネスの世界ではよく使われる言葉ですが、これを日常生活に置き換えると、「いつ、どこで、誰が担当しても、同じような品質や成果を出せる方法を作り上げること」と言い換えることができます。
自分自身への仕組み化
この考え方を自分自身に適用する場合、「やるべきこと(タスク)」を具体的にし、それぞれの作業の質(パフォーマンス)を高め、安定させるために行います。例えば、毎日のルーティン作業の手順を決めておく、目標達成までのステップを明確にする、といったことが挙げられます。これにより、気分や体調に左右されにくくなり、継続が容易になります。
家庭やチームでの仕組み化
家族やチームなど、複数人で生活したり作業したりする場合には、さらに大きな効果を発揮します。「誰がやるか決まっていない作業」を減らし、担当や手順を明確にすることで、作業の押し付け合いや「言った・言わない」といったコミュニケーションロス、それによる喧嘩やトラブルを防ぐことができます。家事の分担ルール作りなどが代表例です。仕組み化は、円滑な人間関係の維持にも貢献するのです。
なぜ大切?仕組み化がもたらす3つのすごいメリット


仕組み化がもたらす安定と効率
日常生活に「仕組み化」を取り入れると、具体的にどのような良いことがあるのでしょうか。そのメリットを端的にまとめると、以下の3つの「力」に頼らなくても、物事がスムーズに進み、安定した成果を出せるようになる点に集約されます。
【仕組み化の3大メリット】
- 能力に頼らない: 特定の人しかできない状況をなくす。
- 意思力に頼らない: 気分やモチベーションに左右されず継続できる。
- 記憶力に頼らない: 忘れっぽさによるミスや漏れを防ぐ。
継続的な恩恵とメンテナンス
これらのメリットに加えて、一度構築した仕組みは、定期的な見直し(メンテナンス)は必要ですが、基本的には半永久的にその恩恵を受け続けられるという点も、非常に大きなメリットです。「頑張る」ことは一時的な効果しか生みませんが、「仕組み」は継続的にあなたを助けてくれます。
QOL向上への貢献
これらのメリットによって、日々の繰り返し作業は効率化され、ミスやストレスが減り、安定した成果を出せるようになります。その結果、時間的にも精神的にも余裕が生まれ、自分が本当にやりたいこと、大切にしたいことにより多くの時間とエネルギーを注げるようになるのです。これが、仕組み化がQOL(生活の質)向上に繋がる理由です。次のセクションから、3つのメリットをさらに詳しく見ていきましょう。
メリット1:個人の「能力」に頼らず安定した成果を出せる


「あの人しかできない」からの脱却
仕組み化の大きなメリットの一つは、個人の「能力」や経験に依存せずに、安定した成果を出せるようになることです。特定の作業が「あの人しかできない」「あの人が一番うまい」という状態(属人化)は、一見するとその人の価値が高いように見えますが、家庭やチーム全体で考えるとリスクがあります。もしその人が不在になった場合、その作業が滞ってしまう可能性があるからです。
誰がやっても同じ成果を出す工夫
仕組み化を進めることで、作業のやり方や手順、判断基準が明確になります。これにより、経験の浅い人や初めてその作業を行う人でも、熟練者と同じようなレベルの成果を出すことが可能になります。これは、個人の経験や勘に頼る部分を減らし、「決まった手順通りに進めれば良い」状態を作ることで実現します。
日常生活での具体例
日常生活においては、以下のような場面でこのメリットを実感できます。
【能力に頼らない具体例】
- レシピ通りに作れば、誰でも同じ味の料理が再現できる。
- 買い物リストがあれば、誰が買い物に行っても買い忘れがない。
- 掃除の手順書があれば、誰が掃除しても同じレベルで綺麗になる。
人はそれぞれ得意不得意があります。一部のできる人に負担が集中したり、その人がいないと回らなかったりする状況を避けるためにも、誰が担当しても一定の質を保てる「仕組み」を作ることが、安定した日常生活を送る上で非常に大切なのです。
メリット2:「意思力」に頼らずラクに継続できる


「頑張る」ことの限界
新しい習慣を始めようとしたり、目標に向かって努力しようとしたりする時、「よし、やるぞ!」という強い意志を持つことは大切です。しかし、その「意思力」だけに頼って物事を継続しようとすると、多くの場合、途中で挫折してしまいます。なぜなら、私たちの意欲やモチベーションは、日々の体調や気分、外部環境の変化によって、常に変動するものだからです。「今日は疲れているから」「気分が乗らないから」といった理由で、簡単に中断してしまうのです。
意思力に頼らない仕組みの力
仕組み化の第二のメリットは、この不安定な「意思力」に頼らなくても、やるべきことを淡々と実行し、継続できるようになることです。作業の手順やタイミング、環境などをあらかじめ設定しておくことで、「やるか、やらないか」をその都度判断する必要がなくなり、自動的に行動を促すことができます。これにより、多少調子が悪かったり、気分が乗らなかったりする日でも、いつもと同じように作業を進め、安定した成果を出すことが可能になります。
日常生活での具体例
日常生活で意思力に頼らずに継続するための仕組みとしては、以下のようなものが考えられます。
【意思力に頼らない具体例】
- 一人だと挫折しそうなら、友達と一緒に運動する約束をする。
- 自分に甘えが出ないよう、目標を周りの人に宣言する。
- ジムの契約や講座の申し込みなど、やらざるを得ない環境を作る。
- 特定の時間になったらアラームが鳴り、自動的に作業を始めるルールにする。
誰にでも気分の波はあります。その波に左右されずに、安定して目標達成や習慣化を実現するためには、「頑張る」こと以上に、行動を後押しする「仕組み」を作ることが不可欠なのです。
メリット3:「記憶力」に頼らずミスや忘れ物を防げる


「覚えているはず」という落とし穴
一度聞いたり、理解したりしたことでも、時間が経つと忘れてしまうのは人間の自然な性質です。「ちゃんと覚えているつもりだったのに」「メモしたはずなのに見当たらない」といった経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。特に、日常生活では多くの情報やタスクに囲まれているため、すべてを正確に記憶し続けることは非常に困難です。記憶力だけに頼っていると、約束を忘れたり、作業手順を間違えたり、必要なものを買い忘れたりといったミスが発生しやすくなります。
記憶に頼らない仕組みの構築
仕組み化の第三のメリットは、この不確かな「記憶力」に頼らなくても、やるべきことを確実に実行し、安定した成果を出せるようになることです。情報を頭の中だけで保持するのではなく、外部のツールやシステムを活用して、必要な時に必要な情報にアクセスできる状態を作ります。これにより、「覚えているか、いないか」という不安から解放され、安心して作業に取り組むことができます。
日常生活での具体例
日常生活で記憶力に頼らずにミスや忘れ物を防ぐための仕組みとしては、以下のようなものが考えられます。
【記憶力に頼らない具体例】
- 予定やタスクを忘れないよう、スマホのアラームやリマインダー機能を設定する。
- 重要な約束事は、相手に事前連絡をお願いしておく。
- 複雑な作業の手順は、チェックリストやマニュアルとして記録しておく。
- 買い物リストを作成し、出かける前に必ず確認する習慣をつける。
- 物の定位置を決め、使ったら必ずそこに戻すルールにする。
人間の記憶は不完全であることを前提とし、それを補うための「仕組み」を作ることが、日々のミスを減らし、安定した生活を送る上で非常に重要なのです。
実践!日常生活で仕組み化を進める3ステップ徹底解説


仕組み化の重要性やメリットを理解したところで、次はいよいよ「どのように仕組み化を進めていくか」という具体的な方法について解説します。難しく考える必要はありません。仕組み化には、効果的に進めるための基本的な手順があります。
ここでは、その手順を「仕分け」「仕組み化」「メンテナンス」という3つのステップに分けて、それぞれ具体的に何をすべきかを詳しく説明していきます。このステップに従って進めることで、あなたも日常生活に効果的な仕組みを取り入れることができるはずです。
ステップ1:まずは日々の作業を「仕分け」て分類しよう


なぜ「仕分け」が必要なのか?
仕組み化を進めるにあたり、最初に行うべき重要なステップが、日々の様々な作業を性質ごとに「仕分け」て分類することです。なぜなら、すべての作業が同じように仕組み化できるわけではなく、作業のタイプによって適した仕組み化の方法や、得られる効果の大きさが異なるからです。やみくもに仕組み化しようとするのではなく、まず対象となる作業の特性を理解することが、効果的な仕組み作りの第一歩となります。
作業タイプの分類方法
日常生活で行っている作業を、1日、1週間、1ヶ月といった期間で振り返り、以下の2つのタイプに分類してみましょう。
【作業タイプの分類】
- ルーティン作業: 決まった間隔(毎日、毎週など)で、ほぼ同じ内容を繰り返す作業。(例:ゴミ出し、洗濯、定例報告書の作成、請求書処理など)
- ルーティン以外の作業: 頭を使って考える必要がある作業、創造性が求められる作業、相手がいて自分の都合だけでは進められない作業。(例:新しい企画の立案、トラブル対応、交渉、家族会議など)
仕組み化の効果が高いのは?
このうち、仕組み化の効果を特に実感しやすいのは「ルーティン作業」です。毎回やる内容がある程度決まっているため、手順やタイミングを標準化しやすく、効率化やミスの削減に繋がりやすいのです。もちろん、ルーティン以外の作業も、ある程度進め方や考え方の「型」を作ることは可能ですが、まずは効果の出やすいルーティン作業から仕組み化に取り組むのがおすすめです。この「仕分け」によって、どの作業から仕組み化に着手すべきか、優先順位をつけることができるようになります。
ステップ2-1:仕組み化の基本!作業を「標準化」する(5W1H)


「標準化」とは何か?
仕組み化のプロセスにおいて、最初に行う具体的なアクションが「標準化」です。これは、各作業の内容や進め方を明確に定義し、誰が担当しても、いつ行っても、ある程度同じように実行できるように基準を定めることを意味します。「なんとなくやっている」「その場の判断でやっている」状態から脱却し、作業のやり方を具体的に決めることが目的です。
5W1H+αで作業を明確にする
標準化を進める上で非常に有効なフレームワークが「5W1H」です。各作業に対して、以下の項目を具体的に決めていきましょう。
【5W1H+αで決めること】
- When(いつ): その作業をいつ開始し、いつまでに終えるのか?頻度は?
- Where(どこで): その作業をどこで行うのか?
- Who(誰が): その作業の担当者は誰か?(自分自身、家族、外部委託など)
- What(何を): 具体的にどのような作業内容を行うのか?
- Why(なぜ): その作業を行う目的や理由は何か?(特に他者に依頼する場合に重要)
- How(どのように): 具体的な手順や方法、使用する道具は?
- (+α)How Check(どのように確認): 作業が完了したことをどのように確認するのか?品質基準は?
標準化のポイント
特に重要なのは、「When(いつ始めるか、いつ終えるか)」と「What(何をやるか)」「How(どのようにやるか)」を明確にすることです。作業の開始・終了条件が曖昧だと、仕組みを作っても実行されない可能性があります。また、他者に作業を依頼する場合は、「Why(なぜ)」の部分を共有することで、作業の意義を理解してもらい、より主体的に取り組んでもらいやすくなります。この標準化によって、作業内容が具体的になり、仕組み化の基礎が固まります。
ステップ2-2:誰でもできるように「マニュアル化」するコツ


「マニュアル化」の目的
標準化によって作業の5W1Hが決まったら、次はその内容を誰が見ても理解でき、実行できるように「マニュアル化」します。マニュアル化の目的は、標準化された作業内容を形に残し、いつでも参照できるようにすることで、作業の再現性を高め、知識やノウハウを共有することにあります。せっかく良いやり方を決めても、それが担当者しか知らなかったり、時間が経って忘れてしまったりしては、仕組み化した意味が薄れてしまいます。
マニュアル化で明確にすべきこと
具体的にマニュアルとして残しておきたい情報には、以下のようなものがあります。
【マニュアル化で明確にすること】
- 作業の手順: 具体的なステップを順番に分かりやすく記述する。
- 作業のポイント: 各ステップでの注意点やコツ、判断基準などを加える。
- 作業の関係性: その作業の前後の工程や、関連する他の作業との繋がりを示す(フローチャートなども有効)。
- 必要なツールや情報: 作業に必要な道具、参照すべき資料、連絡先などを明記する。
日常生活での簡単なマニュアル化
「日常生活の作業にそこまで本格的なマニュアルは作れない」と感じるかもしれません。もちろん、全ての作業で詳細な文書を作成する必要はありません。大切なのは、「標準化した内容を忘れずに、誰でも(未来の自分も含めて)実行できるようにしておく」という意識です。例えば、「この料理はこのレシピサイトを見て作る」「ゴミ出しの曜日はカレンダーに書いておく」「家電の使い方は取扱説明書の該当ページに付箋を貼っておく」といった簡単な方法でも、十分にマニュアル化と言えます。自分や家族が分かりやすい形で記録に残すことが重要です。
ステップ2-3:もっと楽に!便利な「ツール化」を進める方法


「ツール化」で効率と質を上げる
標準化とマニュアル化によって作業のやり方が明確になったら、最後の仕上げとして「ツール化」を検討します。これは、定義された作業を、より少ない労力で、より短時間で、より高い品質で、あるいはより確実に実行するために、適切なツール(道具、機器、ソフトウェア、アプリなど)を導入・活用することを指します。手作業やアナログな方法で行っていた作業を、ツールの力で自動化・効率化・高度化できないか、という視点で考えます。
ツール化の具体例
日常生活におけるツール化の例としては、以下のようなものが挙げられます。
【ツール化の具体例】
- スマホアプリの活用: リマインダーアプリで予定を通知、家計簿アプリで収支管理、タスク管理アプリでToDo整理など。
- 便利家電の導入: ロボット掃除機で床掃除自動化、食洗機で食器洗い自動化、洗濯乾燥機で洗濯物干し不要化、自動調理鍋で料理の手間削減など。
- テンプレートの活用: 定型的なメールや書類作成のためにテンプレートを用意しておく。
- チェックリストの活用: 持ち物確認や作業手順確認を確実に行う。
ツール導入の注意点:目的を見失わない
ここで非常に重要なポイントがあります。それは、「まず標準化・マニュアル化ありきで、その上でツール化を検討する」という順番を守ることです。「このツールが便利そうだから使ってみよう」と、ツール導入から始めてしまうと、本来やる必要のない作業のためにツールを導入してしまったり、ツールの機能に振り回されてしまったり、結果的に非効率になる可能性があります。あくまで「やるべき作業(What, How)を明確にし、そのパフォーマンスを高めるためにツール(How)を検討する」という順番を意識することが、効果的なツール化の鍵となります。
ステップ3:作った仕組みを育てる「メンテナンス」の重要性


仕組みは「作って終わり」ではない
仕組み化のプロセスは、一度仕組みを作り上げたら完了、というわけではありません。本当に効果を発揮し続ける「使える仕組み」にするためには、構築した仕組みを定期的に見直し、改善していく「メンテナンス」のステップが不可欠です。なぜなら、私たちの生活環境や状況は常に変化しますし、実際に運用してみることで初めて見えてくる問題点や、もっと良い方法が見つかることも少なくないからです。
定期的な見直しでレベルアップ
「とりあえず仕組みを作ってみて、実際に動かしながら問題点や改善点を探し、修正していく」という姿勢が重要です。完璧な仕組みを最初から作ろうとするのではなく、まずは動かしてみて、PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回しながら、仕組みを育てていくイメージを持つと良いでしょう。
【メンテナンスで見直すポイント例】
- もっと効率的な手順や方法はないか?
- 誰がやっても、本当に同じようにできるか?(分かりにくい点はないか?)
- 仕組みを維持するために必要な道具や情報は揃っているか?古くなっていないか?
- そもそも、この仕組み(作業)自体がまだ必要か?
改善を続けることの効果
「継続的に見直すなんて面倒くさい」と感じるかもしれません。しかし、多くの場合、最初に作った仕組みは完璧ではありません。運用する中で出てきた問題点を2回、3回と改善していくうちに、その仕組みはどんどん洗練され、より楽に、より効果的に機能するようになります。改善を重ねるほど、仕組み化の効果をより大きく実感できるはずです。作った仕組みに固執せず、常に「もっと良くするには?」という視点を持ち、改善し続けることが、仕組み化を成功させる最後の鍵となります。
仕組み化を成功させるコツとQOL向上への効果


仕組み化は、日常生活をより良くするための非常に強力なアプローチですが、その効果を最大限に引き出し、無理なく継続するためには、いくつか意識しておきたいコツがあります。
ここでは、仕組み化を成功させるための具体的な2つのコツと、仕組み化がいかに私たちのQOL(生活の質)向上に繋がるのかを改めてまとめます。これらのポイントを押さえることで、仕組み化が単なる作業改善ではなく、あなたの毎日をより豊かにするための実践的な知恵となるでしょう。
コツ1:急な予定にも慌てない!「突発対応時間」を確保する


計画を狂わせる「突発的な用事」
どんなに計画的にスケジュールを組んでいても、日常生活では予期せぬ用事や割り込みのタスクが発生するものです。「急な来客」「子供の体調不良」「仕事の緊急依頼」など、これらの突発的な出来事にその都度対応していると、元々予定していた作業が中断され、集中力が途切れ、結局どちらも中途半端になってしまう…ということになりかねません。
あらかじめ「バッファ」を持つ
そこで有効なのが、スケジュールの中に意図的に「突発的な用事に対応するための時間(バッファ時間)」を設けておくことです。毎日、あるいは週に数時間でも良いので、予定を詰め込まずに空白の時間を作っておきます。そして、急な用事が発生した場合、それが「今すぐやらなければならない緊急性の高いもの」でない限り、このバッファ時間に回すようにします。
【突発的な用事への対応方針】
- 日程に多少の猶予がある用事: あらかじめ確保しておいた「突発対応時間」で対応する。
- 緊急性が高く、即時対応が必要な用事: その場で対応する(ただし、頻発する場合は仕組みの見直しが必要)。
集中力維持と安定したパフォーマンス
このようにバッファ時間を設けることで、突発的な出来事が発生しても、現在取り組んでいる作業を中断せずに集中して続けることができます。また、精神的にも「何かあっても、あの時間で対応できる」という安心感が生まれ、余裕を持って日々のタスクに取り組めるようになります。結果として、仕組み化によって目指す安定したパフォーマンスの発揮に繋がるのです。
コツ2:習慣化の鍵!ルーティン作業は「時間を固定」する


ルーティン作業を自動化する
掃除、洗濯、ゴミ出し、メールチェック、日報作成など、毎日あるいは毎週決まって行う「ルーティン作業」は、仕組み化の効果が特に現れやすい領域です。これらの作業を効率化し、習慣化するための最も効果的なコツの一つが、「実行する時間や曜日を固定する」ことです。
時間固定のメリット
やるタイミングを固定することには、多くのメリットがあります。
【時間固定のメリット】
- 意思決定コストの削減: 「いつやろうかな?」と考える手間が省ける。
- 作業時間の短縮: 毎回同じ流れで行うことで、作業に慣れてスピードが上がる。
- やり忘れの防止: 決まった時間に行うことが習慣になれば、うっかり忘れることが減る。
- 生活リズムの安定: 決まった時間に決まったことを行うことで、生活にリズムが生まれる。
具体的な実践方法
例えば、「毎朝起きたらすぐに洗濯機を回す」「毎週土曜日の午前中に掃除をする」「毎日寝る前に翌日の準備をする」といったように、具体的なタイミングを決めてしまいます。さらに、スマートフォンのカレンダーアプリやリマインダーアプリに繰り返し設定で登録し、決まった時間に通知が来るようにしておくと、より確実に実行しやすくなります。最初は意識する必要がありますが、繰り返すうちに自然と体が動くようになり、生活の一部として組み込まれていくでしょう。
仕組み化で変わる!QOLを高め充実した毎日を送ろう


仕組み化がもたらす変化
この記事を通じて、「仕組み化」の考え方、メリット、具体的な方法、そして成功のコツについて解説してきました。仕組み化は、単に作業を効率化するテクニックではありません。それは、私たちの日常生活における様々な側面を改善し、QOL(生活の質)を高めるための強力なアプローチなのです。
安定と余裕のある生活へ
仕組み化を進めることで、個人の能力やその時々の意思力、不確かな記憶力に頼ることなく、安定して物事を進められるようになります。これにより、日々のタスクにおけるミスや漏れ、やり忘れが減り、精神的なストレスが大幅に軽減されます。また、ルーティン作業などが効率化されることで、時間的な余裕も生まれます。
本当に大切なことに時間を使う
そして最も重要なのは、こうして生まれた時間的・精神的な余裕を、自分が本当に価値を置くこと、大切にしたいことに使えるようになる点です。それは、家族や友人との時間かもしれませんし、趣味や自己成長の時間かもしれません。仕組み化は、私たちがより主体的で充実した人生を送るための土台を作ってくれるのです。難しく考えすぎず、まずは身近な小さなことから仕組み化を取り入れて、その効果を実感してみてください。
仕組み化で挫折しない! QOLを高める方法まとめ


「頑張っているのに上手くいかない」「つい物事を後回しにしてしまう」そんな悩みを抱えているなら、「仕組み化」があなたの助けになるかもしれません。この記事では、仕組み化の基本的な考え方から、具体的なメリット、実践ステップ、成功のコツまでを詳しく解説しました。
仕組み化とは、能力・意思力・記憶力に頼らずとも安定した成果を出すための方法です。これを日常生活に取り入れることで、作業効率が上がり、ストレスが減り、時間的・精神的な余裕が生まれます。その結果、本当に大切なことに時間を使えるようになり、QOL(生活の質)の向上が期待できます。
この記事の要点
- 仕組み化は「誰がいつやっても同じ成果を出せる方法」を構築することである。
- 能力・意思力・記憶力に頼らず安定した成果を出せるのが大きなメリットである。
- 実践は「仕分け」「仕組み化(標準化→マニュアル化→ツール化)」「メンテナンス」の3ステップで進める。
- 「仕分け」で作業タイプ(ルーティンか否か)を分類する。
- 「標準化」で作業の5W1Hを明確にする。
- 「マニュアル化」で手順やポイントを記録し再現性を高める。
- 「ツール化」で便利な道具やアプリを活用し効率を上げる(ただしツールありきはNG)。
- 「メンテナンス」で仕組みを定期的に見直し改善し続ける。
- 成功のコツは「突発対応時間」の確保と「ルーティン時間の固定」である。
仕組み化は、一度作れば終わりではありません。しかし、改善を繰り返すことで、その効果は着実に積み重なっていきます。難しく考えず、まずは身近な「面倒くさい」「うまくいかない」と感じることから、仕組み化を試してみてはいかがでしょうか。この記事が、あなたがより効率的で、ストレスなく、充実した毎日を送るための一助となれば幸いです。



.png)


.png)







.png)